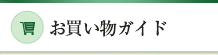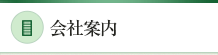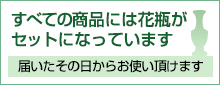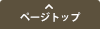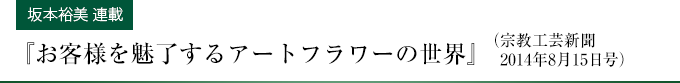
(宗教工芸新聞2014年8月15日号より引用)
はかなさとたくましさ、コスモスの表現力
秋の足音をのせた風に、コスモスの揺れる季節がやってきます。
お仏壇にもそんな気配を届けたくてコスモスをアレンジしてみました。
私にとってコスモスの最初の記憶は、小学校の教科書にあった挿絵です。
お母さんにおんぶされた小さな女の子が駅のホームで、出征しようとするお父さんから、小さな手のひらにコスモスの花を一輪受け取るシーンでした。
永遠の別れという運命を象徴するのは、バラでも菊でもなくコスモスしかないと感じさせるはかなさがあると思います。
ところが、実際のコスモスを一輪で見かけることはほとんどなく、たいていは群生しています。
秋桜というくらいですから、桜のように日本古来の花かと思ったら原産はメキシコで日本に入ったのは明治時代とのこと。
はかないどころか、勢力を伸ばしてきたわけです。
私の故郷の長野県佐久市の市花がコスモスで、内山という地区に大規模なコスモス街道があります。
道路の両側から休耕田までが一面のコスモス畑。
よく手入れされたコスモスは、背が高くて凛としたたくましさにあふれています。
強い風になびくように見えて、実は動じることもない安定感も抜群。
しかも9月の始めころから約1ヶ月もの間咲き続けて人々を楽しませてくれます。
ところでコスモスは、前回のヒマワリと同じくキク科に属す花です。
規則正しく並んだ8枚が花びらのように見えますが、これはキク科の花に共通のトリックのようなもの。
小さな花びらの集合体の中の一番外側の花の一部が大きく発達した形状なのです。
同じコスモスなのに花の色によって花言葉が違ったり、一般的に一年草なのに、チョコレートの色のだけが多年草だったりと、コスモスは芸達者です。
そんなコスモスですから、自由に共演できるようにほんの少しだけ演出するだけにしました。
もちろん造花ですが、はかなさとたくましさがきちんと表現されていれば幸いです。
ご先祖さまも楽しんでくれるに違いありません。
(坂本裕美 アートフラワー作家 カラコレス代表)
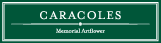
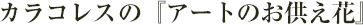
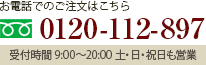
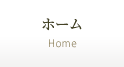
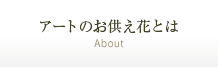
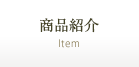
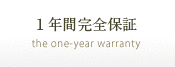

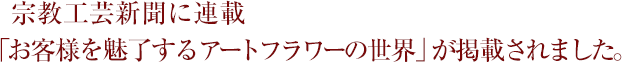

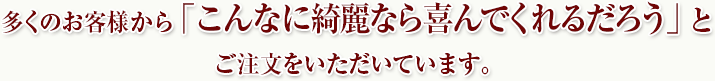
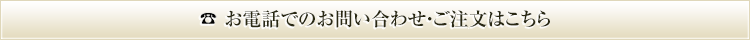
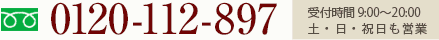
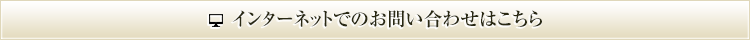

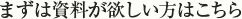
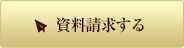
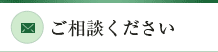
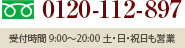
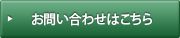


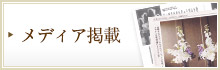
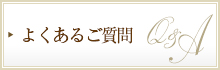


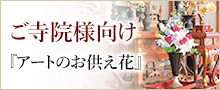
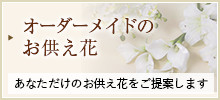
![[代金引換] [銀行振込] [クレジットカード]](/common/images/side_pay2.png)
![[全国送料無料][代引手数料無料]](/common/images/side_pay3.gif)